はじめに
今回は、ちょっと色々あって、Web関係のうち特に、いわゆるアフェリエイトブログ関係に詳しい人の話を聞いたのですが、余りにちょっとアレだと感じたので、メモしておきます。
ちなみに、初めに言い訳をしておきますと、国の著作権には割と大らかな国柄を反映してか、なぜか弁理士試験における著作権法の扱いは、高校の通知表の体育、美術くらいの立ち位置だったりします。具体的には、おまけレベルの扱いで、その後実務で使う人もほとんどいないと思います。
アフェリエイトブログとは
いわゆるアフェリエイトブログとは、ブログに広告や販促リンクを張って、他者のアクセスによりお金を稼ぐタイプのブログです。
実はこの界隈は、著作権も真っ青のパクりあいになっており、執筆依頼を受けると、普通にWikipediaや、具体的なサイトの指定の元に、リライトのような形で量産されているようなんですね。っていうか、元々同じことについて精度を高く書いていけば、結局ある程度同じものにはなってしまうとは思うのですが。
もちろんそのままパクればばれてしまうので、色々なテクニックが使われているようです。具体的には、無難な辺りで情報の追記です。元の記事にない情報を、元の記事の文章に追加して記載します。まあ、分かります。
しかし、ここからが酷く、語尾や言い回しの変更、同義語への書き換え、複数サイトを参照しての合成などなど、実質パクりだけど、そうは見えないからOKみたいな手法が、平気で指導されているそうです。
検索エンジンの対応
ところで、このようなパクりサイトに対するグーグルとかの検索エンジンの対応は、パクり認定をした場合に、パクりサイトの評価を下げるルーチンを導入したりする形のようです。アフェリエイトサイトは、ユーザーのアクセスを得ることで、収入を得るタイプですから、当然検索エンジンからはじかれては、儲けることが出来ません。
また、実際には、パクりの再生産をしているだけですから、普通に記事を量産したらパクり判定になってしまうのは明確です。
では、アフェリエイトサイトは、どのようにパクり認定を回避しているのでしょうか。実は、編集用のパクり判定ツールみたいなものが出回っているようなのです。一例では下記のようなサイトがあります。
〇CopyContentDetector:
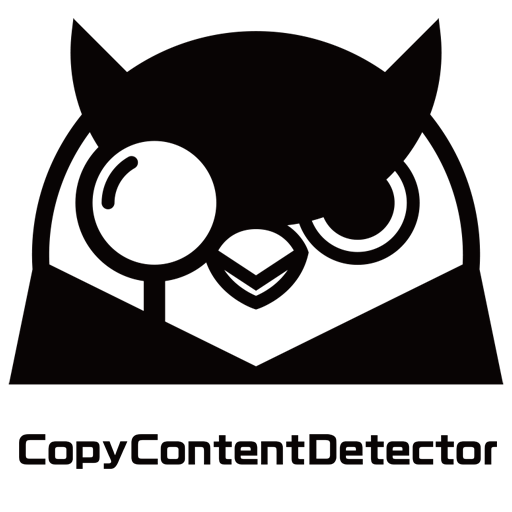
この辺は、特定の文章を指定して、より精度を上げて判定するようなツールもあり、例えばWikiPediaの該当項目をコピーしてきて、判定したい文章と突き合わせるようなことも可能です。この手のツールについての紹介は、ここでは割愛します。依頼者ごとに、この手のパクり判定ツールで一定の割合以下なら掲載OKとかしているそうです。
いや、そうじゃねーだろ。
なぜパクりサイトはダメなのか
ところで、なんでパクりサイトは、ダメなんでしょうか。常識、良識、パクって書いても面白くないなどなどあると思いますが、大体著作権的にダメだからというような人も多いと思います。
他の国の著作権は、良く知らないんですが、とりあえずこの国の著作権の目的は下記になっています。
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
超雑には、著作物に該当するものに対する著作者の権利を保護します、みたいな感じのようです。アフェリブログの話に振り返ってみると、最初に例えばWikipediaの文章が著作物に当たるなら著作物で、その文章を書いた人が著作者なんじゃないでしょうか。
どういう場合に著作者が保護されないかっていえば、例えば、さっきの例で当てはめていくと、著作者が頑張って書いた文章が、アフェリエイトサイトにパクられて、著作者には1円にも入っていないのに、アフェリエイトサイトに収益が発生してしまうような場合の気がします。
つまり、パクり判定サイトの判定が一定数値以下かどうかは、別として、パクって書いたものでお金儲けをしてはいけないのではないでしょうか。
結果的に同じに文章なってしまった場合
じゃあ、結果的に同じ文章になってしまった場合は、どうすれば良いのでしょうか。前述の通り、同じものに対して、同じような情報を入手して、同じような精度でSEO対策とかを考慮して書いたら、結果的には、同じような文章になることは、当然あるわけです。この辺は、どうなってしまうのでしょうか。
実は、さっきのパクりサイトがWikipediaをパクる所から始めて参照しながら書くみたいなことは、依拠性と呼ばれているようです。この辺は、実は著作権法の条文には1文字も出てこないのですが、その筋では軽く有名なちょっとぐぐると大量に出てくる下記のような判例が手掛かりになるのかもしれません。
〇Wikipedia「ワン・レイニーナイト・イン・トーキョー事件」
趣旨だけを超雑に拾いますと、「既存の著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは、その複製をしたことにはあたらず、著作権侵害の問題を生ずる余地はない」っていうことですね。
つまり、自分で考えて書いたりしたものが、偶然他の人と似てしまったような場合は、セーフと言う訳です。実際これは、前述の通りどうしようもないですしね。
逆に言えば、最初からパクるところからスタートして、パクり判定を回避しようとしているパクりサイトは、この話の真逆を行っているのではないでしょうか。まあ、検索サイトのパクり判定さえ回避できればOKということなのかもしれませんが、それはそれで、社会の仕組みとしてどうなんでしょうね。
ちなみに、この判例の射程の範囲は、個別の事案の対象や条件によりますので、お金が絡んでいる場合はご自身で再確認された方が良いと思います。
まとめ
パクり系のアフェリエイトサイトの闇は濃そうですね。
kuroneko
最新記事 by kuroneko (全て見る)
- 界の軌跡は軌跡シリーズの根幹がひっくり返る話でした。 - 2025年12月22日
- 浅草は相変わらず凄い人でした。 - 2025年10月23日
- 鎌倉は物凄い混んでる観光地でした。 - 2025年10月13日


